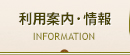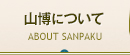教育・学習支援R・Sさん
今回の博物館で博物館の開館の準備から展示に対する認識、研究活動などにどのように向き合うかについて学ぶことができました
博物館の開館前には、館内の異常がないか確認し、照明やエアコンの動作確認を行いました。その際、空調機器の老朽化が進んでおり、気象条件の変化に伴ってエアコンの使用が必要であることが指摘されました。実際、実習中にもエアコンが使えなくなることがあり、早急な対策が必要だと感じました。大町山岳博物館では、ライチョウやカモシカの飼育、高山植物の栽培を見学し、ライチョウの人工孵化や野生復帰に向けた取り組みについて学び、博物館と他施設の連携の重要性を実感しました。また、山岳図書資料館では、寄贈された資料の保管状況を確認し、資料が適切に収蔵できていないという課題を認識しました。害虫対策として、収蔵庫前にトラップが設置され、収蔵庫内の温湿度管理が行われていることを確認しました。
実習では、さく葉標本の作製を行い、標本を台紙にマウントし、ラベル添付やナンバリングを体験しました。この作業では経験が非常に重要であることを感じ、特殊な紙テープが生産終了となったことで今後の作業が困難になることも学びました。火山灰の分類実習では、椀がけ法を使って採取された火山灰を顕微鏡で種類別に分類する作業を体験し、似た岩石の区別が難しいと感じました。人文資料の仮登録作業では、資料の整理とラベリングに時間と根気が必要であり、来館者には見えにくいが重要な作業であることを学びました。山岳博物館には、アイゼンやピッケルなどの山岳資料が多く、これらの特徴を記録するために絵を描く作業が求められましたが、絵を描くことが苦手だったため難しさを感じました。
自然ふれあい講座「セミの抜け殻を探せ」では、子供たちが参加するイベントの補助を行い、自然の変化とセミの種類や数との関係を調べる活動を支援しました。子供たちに集中力を持たせ、興味を引き出すことの難しさを感じつつも、工夫しながらイベントに関わりました。参加した子供たちが楽しんでいる様子を見て、自然に対する興味を持ち続けてほしいと感じました。
実習最終日には、来館者に展示を解説するスポットガイドを行い、地形の成り立ちや生態系について説明しました。事前に資料を読み、展示物と関連づけて解説内容を準備しました。見学者との対話が大切であり、知識量の違いを考慮して解説する必要があることを学びました。
6日間の博物館実習を通じて、博物館で学芸員として働くとはどういうことなのかを学ぶことができました。また、地方にある博物館が現在直面している課題についても、現場を見ることで改めて確認することができ、課題解決に向けた働きかけを進めていくことの重要
性を感じました。大町山岳博物館での学芸員実習は、自然と登山文化に深く関わる貴重な体験であり、日本アルプスの豊かな自然や地域の歴史に関する知識を深める機会となりました。また、来館者への案内や教育プログラムの支援を通じて、地域の文化や持続可能な登山活動の重要性についても学びました。さらに、地域住民との交流を通じて、地域の特性や課題についての理解を深めることができました。この実習を通じて、博物館運営の実務や社会貢献の意義についても学ぶことができ、貴重な経験となりました。最後に6日間という期間、博物館実習を受け入れていただき、ご指導いただいた市立大町山岳博物館職員のみなさま、一緒に実習を行った4名の実習生に厚くお礼申し上げます。