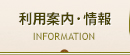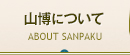教育・学習支援I・Tさん
1 はじめに
本稿の目的は市立大町山岳博物館における実習を通して学んだ、博物館の果たす役割や、その中で学芸員が果たす役割とは何か、またその実情ついて述べることである。
2 実習の概要
市立大町山岳博物館における実習は、7月30日(火)から8月4日(日)までの6日間行われた。実習内容については以下の通りである。
(1) 7月30日
初日は館の成立ちや特色について説明を受けた後、収蔵庫等の博物館の裏側を含めて案内・説明を受けた。その後、「調査・研究事業の概要」として、山岳博物館が全国に先駆けて行ってきたライチョウの人工飼育について説明を受けた。
(2) 7月31日
2日目は「収蔵・保管事業の実習」として、近隣で採集してきた植物を標本にする作業を行った。その後「調査研究事業の概要」として、市内の地層から採集した土から鉱物を取り出し、観察を行った。最後に「教育・普及事業の概要」として、山岳博物館が日頃取り組んでいる展示のポイントや学校教育との連携について説明を受けた。
(3) 8月1日
3日目については、各自で近隣の博物館を訪問し、各博物館についての展示資料や展示の特色等について考察を行った。近隣の博物館として「塩の道 ちょうじや」「安曇野市豊科郷土博物館」「旧中村家住宅」の3館を訪問した。
(4) 8月2日
4日目は「収集・保管事業の実習」として、人文科学系の資料、とくに登山史資料についてサイズの計測やスケッチ等の資料整理(ピッケルやアイゼン等)を行った。
(5) 8月3日
5日目は教育普及活動の補助として、自然ふれあい体験の補助を行った。この体験講座では、子供たちと博物館周辺の森林にて、セミの抜け殻を採集し、その特徴を観察することにより種の同定を実施した。実習生については、各家族へ付き添い、抜け殻探しや種の同定について助言などを実施した。このセミの抜け殻集めは例年実施しており、年々温暖化のために生息している種類が変化していることを説明した。
その後、スポットガイドの準備として、実習生同士でガイドを実施し、お互いの講評を行った。
(6) 8月4日
最終日は前日実習生同士で行ったスポットガイドについて、実際に来館者へも実施した。また、館の受付・案内についても実施した。
3 実習を通じて学んだこと
(1) 博物館の地域における役割について
今回の実習において、学芸員の方々から「市立の博物館であることを常に念頭においている」旨説明を受けた。それ故、2日目の実習(植物標本作りや鉱物の観察)の素材はすべて市内で採集されたものであった。こうした取組は、市立博物館として、地域の資料=資源を中心に研究、保管、展示を行うことを重要と考えている結果であると考えられる。
こうして収蔵された資料により山岳博物館を展示・解説を実施していたが、来館者は市民と観光客(主に登山客)の2パターンがおり、それぞれに博物館は違った働きかけにより地域を知ってもらう仕組みを作っていた。
市民に対しては、例えば、展示物の中には、高山帯にある動植物のみならず、普段人間が生活している地域(山麓)にある動植物や鉱物の展示もあり、地域で生活する市民も興味深く展示を見ていた。こうした身の回りの動植物から展示を見始めて、高山帯の動植物や鉱物を観察することで、市民は自分の住み環境を相対化しその特色を理解するとともに、普段目にする山岳というものへの興味を持つきっかけ作りにもなっていた。また、自然ふれあい体験のように、普段何気なく見ている身の回りの自然も、専門家の観点からみると様々な気付き(セミの生態や温暖化の問題等)があることが示され、特にこども達にとってはセミの抜け殻集めという日常が、学問の世界への入口となっており、市民への教育的な意義が大きいものであった。市民の日常を起点とした教育活動は、市民にも親しみやすく、効果的な教育活動が実施できるものと思われる。
一方で観光客相手では、こうした普段の身の回りを起点にした展示というよりも、山岳を起点とした展示になっていた。観光客は自分達が訪れた山々の環境を起点として、市民たちとは逆に山麓環境を新たに知り、山岳の特色を理解するようになっていた。すなわち、観光客(=登山客)にとってある意味自分達に親しみのある周辺環境である高山帯を起点として、その山麓地域を知り、大町市という空間を理解していた。
山岳博物館の展示の特徴として、大町市を中心に、山麓から高山帯までの展示になっていたため、市民は山麓を起点に、観光客は高山帯を起点に展示を見ることができるようになっている。こうした展示構成から、市民は自分の周辺環境の特色を、観光客は高山帯の特色をそれぞれ理解するとともに、さらにその外縁にある環境(市民にとっては高山帯、観光客にとっては山麓地域)を新たに知ることで、地域全体を理解することができるようになっていた。山岳博物館は地域において、市民にとっても観光客にとっても地域を包括的に知るきっかけ作りをする場としての機能を果たしていた。
(2) 博物館における学芸員の役割について
収集・保管事業においては自分の仕事が他館の学芸員や研究者、ひいては後世の人々の目に触れられることを意識していることを学んだ。例えば資料の整理表へより詳細に、あらゆる情報を記載するという姿勢や、植物標本のラベル(採集地や年月日を記載する)に書くのに用いるペンも長期間の保存に耐えうるインクを用いている旨説明を受け、普通の仕事よりも長い時間軸を意識して責任を持って作業にあたっていることが分かった。博物館には数多くの資料が収蔵されているが、それらの資料が全てこうした配慮を経て収集・整理・保管されていることを理解したと同時に、その価値が分からない者に誤って廃棄されてしまう事件が度々起きていることも紹介された。博物館資料の中には、一見して地味で目立たないものもあるが、それぞれの館がこだわりと責任をもって収集し、保管している重要な資料であることを実感した。
調査・研究業務において、収蔵されている資料をどのように活用しているかを学んだが、例えばライチョウの飼育においては、当初飼育データを内部情報としてしまったが故に、各専門家からの多角的な分析ができず、失敗に終わってしまった旨説明を受け、積極的に他の博物館や大学等の研究機関との共有を図ることが重要であることを理解できた。
教育・普及活動に係る実習の中では「単に聞かれたことに応えていては、その方の生涯学習にとって良くない」という言葉が印象的だった。答えを単に教えるだけが生涯学習につながるものではなく、その人にとっての最適な学びとは何かを考え、一人一人にあったヒントや参考資料の提供を行い、自発的な学びを促進することが重要であることを学んだ。
スポットガイドでは、実際に来館者の方を相手に資料の解説を実施したが、来館者の方が持っている基礎知識や興味関心がそれぞれ異なっており、そうしたいわば相手の技量をくみ取って解説を行うことが重要であると学んだ。すなわち、一方的な知識の押し付けではなく、相手の表情や受け答え、時にはこちらから質問を投げかけることにより、相手の興味関心や知識量を推し量り、それに応じた資料説明を行うことが重要であると理解した。実習を行うまでは、学芸員に必要なのは資料に関する知識量だと思っていたが、最も重要なのは「観察力」(人間に対しても資料に対しても)であると考えを改めるきっかけとなった。
学芸員は博物館の根幹である資料の収集・保管、調査・研究、教育・普及活動を担う存在であるが、資料の収集・保管には長い年月を見越した配慮が必要であり、そうして得られたデータや知見を各機関と連携して共有することで、調査・研究が深化し、よりよい展示や資料の解説にもつながっていくことを学んだ。
(3) 地方公立博物館の実情について
今回の実習を通じて、山岳博物館の職員から、折に触れて「地方の公立博物館の実情」を伝えていただいた。例えば、博物館の収蔵庫には、未整理の資料や寄贈された資料で溢れかえっていたが、この要因としては、本来学芸員の最も重要な仕事である、収集・保管業務が、他の事務仕事により圧迫され手を付けられないでいることがあった。実習をしていて最も感じたのはよく言われるように学芸員は、まさに「雑芸員」であるということだった。例えば朝の館内の掃除や学校行事における学校側との調整等は、すべて学芸員が担っており、とても専門職とは思えないほど多様な業務を担っていることを理解した。
また、設備も相当老朽化しており、収蔵スペースが十分でないこともあり、多くの資料が空調機能のない部屋に保管されていた。特に人文系の資料に関しては、新たな資料の収集予算が基本的にゼロであることから、寄贈による資料収集しかできない状況であることを教えていただいた。一方で、博物館法の改正により、今後は観光施設等とも連携して、地域振興に係る業務を行わなければならないこともあり、現場は相当疲弊していることが理解できた。そうした中で、博物館の最も助けになっている存在が「友の会」であり、館周辺の環境整備(草刈り等)から、資料整理の手伝いまで、幅広に支援していることが分かった。実習に行くまで、「友の会」の存在は知っていたが、博物館の運営にここまで大きな役割を果たしていると思わなかったため、友の会の活動について興味を持つきっかけになった。
4 おわりに
本稿では、博物館実習において学んだことについて、博物館の果たす役割、学芸員の果たす役割、博物館の実情と3点に分けて述べた。博物館は地域の資源である資料を活用して、その地域の特色を来館者へ展示を通じて伝えていた。来館者はそれぞれの目線から展示を見始め、最終的に大町市という空間全体を理解できるように展示がなされていたことから、博物館は地域の特色を伝える場であると理解した。学芸員は展示を形成する資料を扱っていたが、その取扱いについては長い時間軸での責任が伴うとともに、展示の良しあしもまた、学芸員による資料への調査・研究次第であることが理解できた。
今後は博物館にも地域振興の役割が新たに追加されることとなるが、現行の体制では多くの地方の小規模な博物館は対応ができないものと思われる。こうした実情の中で、どのように対応していくのか、その経過について注視・検討していきたい。