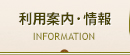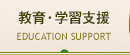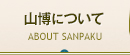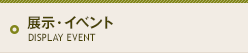北アルプス国際芸術祭 2024 パートナーシップ事業日本人とエベレスト 〜その聖性から大衆化まで〜
会期:2024年10月19日(土)〜12月1日(日)
主催:信州の山岳文化創生会議 / 共催:市立大町山岳博物館
1970 年日本隊の登頂、1975 年女性初登頂など、日本隊の活動を中心に、世界最高峰「エベ レスト」登頂に挑んだ日本人登山家の足跡を紹介する写真展です。

1953(昭和38)年イギリス隊の初登頂から70年の間に、エベレスト※1は大きく変貌してしまいました。その象徴が、2019(令和元)年5月23日、公募登山者を含む354人の登頂です。高度情報化社会の深化と広がりのなかで、大衆化の様相はとまりません。
世界最高峰であるがゆえに、エベレストの「聖性」と、それが失われていく「宿命」と「呪縛」、その過程を、エベレストへ挑んだ日本人登山家の写真を介して追っていきます。
今回の企画展では、1970(昭和45)年日本隊の登頂※2、1975(昭和50)年女性初登頂など、日本隊の活動を中心に、エベレストの聖性から大衆化までの過程を俯瞰した、日本人登山家たちの貴重な写真30数点を展示します。ぜひご高覧ください。
なお、会期中、エベレスト登山に関する講演・シンポジウムも開催します。こちらの企画展関連催しにも、ぜひご参加ください。
※1 エベレスト
標高8,848mの世界最高峰。中国(チベット)名チョモランマ、ネパール名サガルマータ。
各国の登山隊によるエベレスト登頂の歴史は、1921(大正10)年のイギリス隊による第1次遠征から始まり、1953(昭和28)年のイギリス隊による初登頂(登頂者はエドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイ)以後、1956(昭和31)年のスイス隊、1960(昭和35)年の中国隊、1963(昭和38)年のアメリカ隊、1965(昭和40)年のインド隊、そして、イギリス隊のヒラリーとテンジンによる初登頂から17年後、1970(昭和45)年に日本隊による登頂(世界第6登)が続きました。
※2 1970(昭和45)年日本隊の登頂
1970(昭和45)年5月11日に日本山岳会エベレスト登山隊第1次アタック隊員の松浦輝夫と植村直己、翌12日には第2次アタック隊員の平林克敏(長野県大町市出身)とネパール人現地協力者のチョタレーが登頂に成功しました。
この登山隊は松方三郎隊長ら隊員39人で組織され、装備・食糧など約32トンを使用し、その登頂成功は「史上最大規模の物量作戦による」といわれました。同登山隊では、極地法による登山によって、エベレスト南東稜から登頂を果たしました。一方、同登山隊で同時に計画された当時未踏のエベレスト南西壁初登攀は、標高8,050mにまで達しましたが、ルートの状況が悪いことなどで成功には至りませんでした。その後、1993年(平成5)年に群馬県山岳連盟隊によって冬のエベレスト南西壁が初登攀されています。
| 主催 | 信州の山岳文化創生会議 | |
|---|---|---|
| 共催 | 市立大町山岳博物館 | |
| 協力 | 日本山岳会、(株)山と溪谷社、読売新聞社、毎日新聞社、梅棹忠夫・山と探検文学賞委員会 | |
| 会期 | 10月19日(土)〜12月1日(日)※会期中の月曜日は休館。ただし、月曜日が 祝日の場合は開館し、翌日休館 | |
| 時間 | 10・11月:午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) | 12月:午前10時〜午後4時(入館は午後3時30分まで) |
| 会場 | 市立大町山岳博物館 特別展示室 | |
| 費用 | 通常の観覧料(常設展と共通)が必要です | |
解説する展示の一部

チョ・オユーから望むエベレスト西面 (倉岡裕之氏提供)

エベレスト公募登山隊 (2010年、ヒラリー・ステップ付近の登山者たち)

エベレスト南西壁核心部 (山田圭一氏提供)

クーンブ氷河上空からエベレスト頂上(左)など一望した航空写真
関連イベント
講演・シンポジウム
企画展関連催しとして、エベレスト登山に精通し た講師・パネラーをお招きし、会期中に講演・シンポ ジウムを開催します。
| 講演 | 「写真で見るエベレスト日本隊」講師:神長幹雄さん((株)山と溪谷社 元出版部長) |
|---|---|
| シンポジウム | 「エベレスト 聖性からその喪失まで」 パネラー:古野 淳さん(日本山岳会 前会長、日大エベレスト登山隊 北東稜初登攀) / 倉岡裕之さん(登山家・山岳ガイド、エベレスト登頂11回 日本人最多) / 神長幹雄さん(編集者、日本山岳会) コーディネーター:扇田孝之さん(信州の山岳 文化創生会議委員) |
| 主催・共催・協力 | 企画展と同じ |
| 期間 | 11月17日(日) |
| 時間 | 午後1時30分〜午後4時 |
| 会場 | 当館 講堂 |
| 対象・定員 | どなたでも・40名(先着順) |
| 参加費 | 無料 ※企画展の見学には通常の入館料 (常設展と共通)が必要です |
| 申し込み | 11月15日(金)までに電話・FAX・Eメールまたは直接、当館へ
※先着順。定員になり次第締め切ります。
市立大町山岳博物館 電話:0261-22-0211 FAX:0261-21-2133 Eメール:sanpaku@city.omachi.nagano.jp |